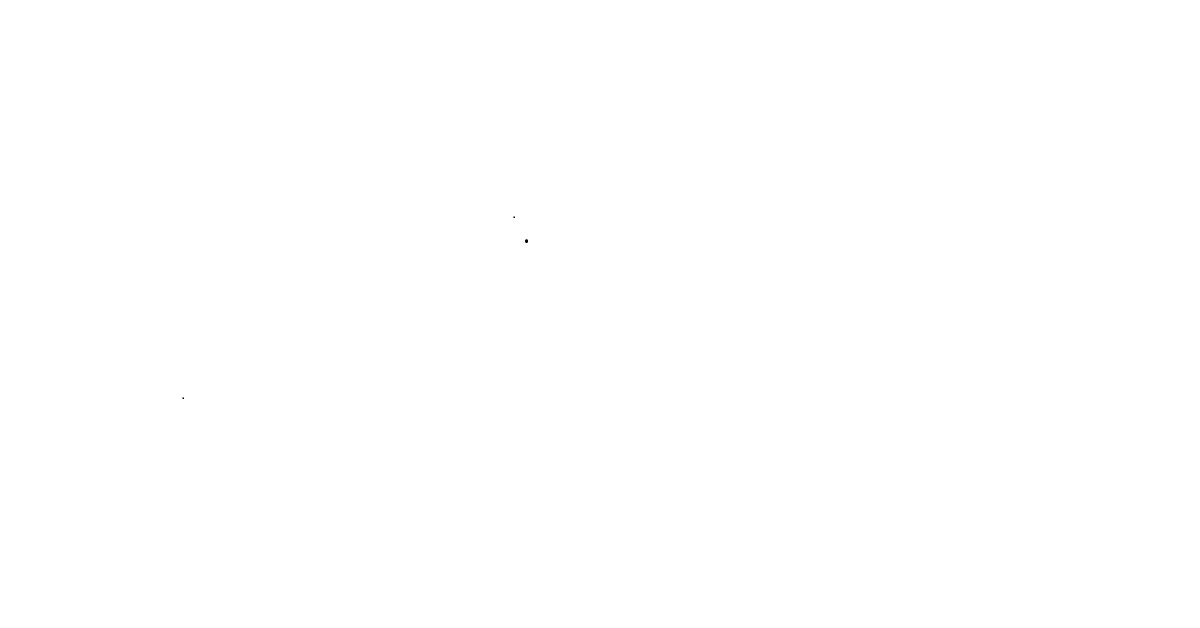猫免疫不全ウイルスと猫白血病ウイルスは野良猫を飼おうとした場合、避けては通れない可能性があるでこの記事を書きました。
※この記事は、犬猫みなしご救援隊の中谷さんのブログ内容を参考にしつつ、筆者自身の経験を交えて執筆しています。
詳しくは元記事をご覧ください: 犬猫みなしご救援隊 中谷さんのブログ
猫免疫不全ウイルス(FIV=猫エイズ)は、1986年に米国で発見されましたが、実は太古の昔から存在していた可能性があります。
中谷さんもブログで述べているように、「弱いウイルスであり、感染している猫を差別的に扱うことの方が問題」と考えられています。
また、猫白血病ウイルス(FeLV)も空気中では不安定で、太陽光や水によって簡単に感染力を失います。
日々の掃除や衛生管理を徹底していれば、生活圏で簡単に広がるものではありません。
◆ 個人の経験から
私自身も野良猫を保護して15匹の猫と暮らしています。
猫同士の喧嘩や縄張り争いで感染の可能性はゼロではありませんが、ウイルスに感染していても発症しない場合が多いことを経験しています。
保護直後は、先住猫や環境に慣れないこともあり、一時的に隔離して様子を見ることもあります。
しかし、発症していない場合は、他の猫と同じ環境で生活させています。
◆ 注意しているポイント
-
大きな喧嘩を避ける
-
ストレスを減らすための環境整備(遊び場やくつろぎスペースの提供)
-
定期的な健康チェックとウイルス検査
こうすることで、猫たちは安心して暮らしながら、発症リスクを最小限に抑えることが可能です。

◆ 完全隔離との違い
中には透明な仕切りを使って完全に隔離する方法を取る方もいます。
確かに接触を避けられますが、猫にとってはストレスになりやすいことも想像できます。
私の場合は、発症リスクが低い場合は隔離せずに同じ空間で生活させる方針です。
◆ 中谷さんの考え
犬猫みなしご救援隊の中谷さんは、FIVやFeLVに感染している猫も積極的に保護・育成しています。
重要なのは「無駄に恐れず、正しくウイルスと向き合うこと」。
感染しているからといって差別せず、公平に扱うことが大切とされています。
まとめ
-
猫エイズ(FIV)や猫白血病(FeLV)は恐れるべきものではあるが、過剰に隔離する必要はない場合もある
-
発症していない猫は、適切な環境と管理で他の猫と共に生活できる
-
個人の経験や専門家の意見を参考にしつつ、猫にとってストレスの少ない方法を選ぶことが大切
私は現在、猫エイズ(FIV)の陽性反応がある猫と暮らしています。
以前にも、発症せずに一生を終えた猫を看取った経験があるため、同じ環境で一緒に生活させています。
もちろん、ウイルスは目に見えず、外出や人間の手を介して持ち込む可能性もゼロではありません。
その点は正直に怖いと思うこともあります。しかし、コロナ禍でもそうだったように、完全な無菌状態で生活しない限り、感染リスクを完全に排除することは難しいのが現実です。
そのため、猫が発症するまでは、できる限り快適で安全な環境で他の猫と共に生活させています。
発症が確認された場合は、もちろん適切に隔離や治療を行う必要がありますが、それまでは理解したうえで共に暮らす選択をしています。
野良猫を保護して暮らす場合、こうした感染リスクも存在することを知っておくことは大切です。
悩んでいる方もいると思いますが、情報を正しく理解し、環境や体調管理に注意すれば、猫との暮らしを安心して楽しむことができます。
このポストを見つけたのですが、多頭飼育崩壊の現場の話ではありますが、猫エイズ(FIV)のウイルスを保有している猫は意外と多く存在することがわかります。
もちろんすべての猫に当てはまるわけではありませんが、保護猫や野良猫と暮らす場合は、このリスクを理解しておくことが大切です。
うちは20頭の多頭飼育崩壊から2匹保護してからエイズとわかりました。
一緒に保護した子は白血病。
白血病発症したので抗がん剤治療始まりました。
みんな仲良く頑張ってください🐱— ゆずりん (@yz0725) July 5, 2025
野良猫の幸せを願っています。