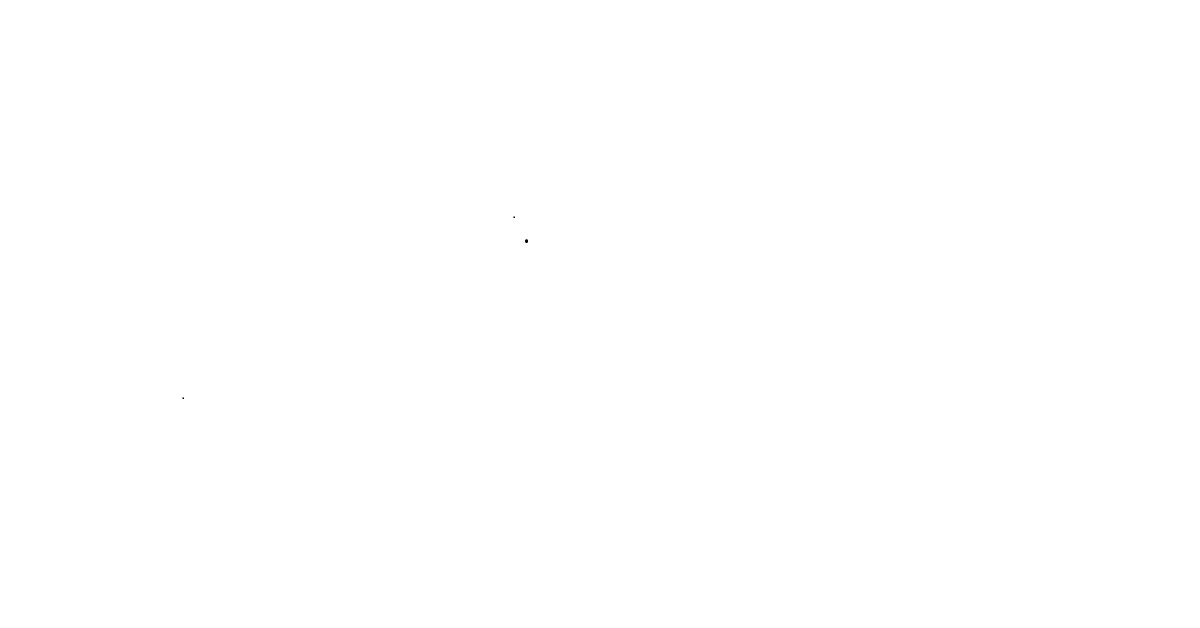ペットや家族を看取るとき、私たちは常に「正しい選択」を迷います。特に安楽死という言葉は、倫理的にも感情的にも重く、決して簡単に判断できません。
私はかつてセントバーナードを訪問安楽死で見送った経験があります。犬は何も語らず、その行為が本当に正しかったのか確信を持つことはできませんでした。しかし、祖母をがんで看取った経験を通じて、人間の声を直接聞くことで、安楽死や終末期ケアについて考えるきっかけを得ることができました。
祖母の闘病生活と声
私の祖母は再発した膀胱がんを患い、やがてリンパに転移しました。痛み止めを打つようになり、体温の低下や血液にカビが生えるなど、体の機能は次第に衰えていきました。
そのとき祖母は、「早くあの世に逝きたいよ」と口にしました。これはただの言葉ではなく、闘病生活で感じた苦しみや限界を示す、切実な声でした。人間としての意思を直接聞いたことで、安楽死や医療介入について考える視点が変わりました。
日本では人間の安楽死は法的に認められていません。私の祖母も例外ではなく、病院で最期を迎えました。死因は誤嚥によるものです。
犬の安楽死との違い
獣医による犬の訪問安楽死では、言葉による意思表示がありません。そのため、飼い主として「これで良かったのか」という葛藤が常に残ります。
一方、人間の場合は、本人の言葉や意思を確認できる分、安楽死や終末期ケアの選択について考えやすくなります。祖母の「早く逝きたい」という言葉は、訪問安楽死や鎮痛ケアの意義を理解する上で、とても重要な指標となりました。
訪問安楽死や終末期ケアは正解でも不正解でもない
私の経験から言えるのは、訪問安楽死は「正解でも不正解でもない、一つの選択肢」であるということです。
-
犬の場合は言葉を発せないため、判断は飼い主に委ねられます。
-
人間の場合は意思を確認できる分、より慎重に考えることができます。
どちらの場合も大切なのは、苦しみを最小限にし、その命に敬意を払うことです。安楽死を選んだとしても、それは愛情に基づく一つの行動であり、後悔や罪悪感を抱える必要はありません。
まとめ
-
安楽死は正解・不正解の二択ではなく、苦痛を和らげるための選択肢
-
人間の癌患者の声を聞くことで、終末期ケアや安楽死の意味を理解しやすくなる
-
ペットの場合は、言葉がないため判断は飼い主に委ねられる
-
最も重要なのは、最期まで尊厳と愛情を持って見送ること
祖母の言葉を聞いたことで、訪問安楽死や終末期ケアは単なる医療行為ではなく、命を尊重するための一つの方法だと強く感じました。犬や家族の看取りに悩む方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
【関連記事】